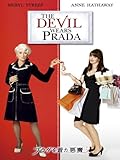CoSTEP (北海道大学 科学技術コミュニケーション教育研究部門) の通信講座、というものをこの1年間受けていました。
私が受講したのは選科B。E-learning での講義の視聴と課題提出、そして秋に3日間のライティングを主とした集中演習を受けてきました。いろいろな演習もあって、人によっていろいろな活動をしている講座ですが、私はe-learningで細々学んでいました。
CoSTEPに関する詳細はウェブサイト「2018年度CoSTEP受講生募集」と、動画を参考にしてください。
無事、課題を出し切って修了したので、この間考えたことをまとめておきます。
明日、26日に、来年度募集に向けた説明会&修了者座談会というのに出るので、その前にこの1年間を整理することも兼ねて、いつか受講しようと思う方の参考になれば幸いです。
- 受講した経緯と応募時に考えていたこと
応募した時にこの講座を通して考えたいと思っていたのは次の2つでした。
- どうやって「科学を伝える」ことに携わっていけるか探ること。
- 研究所、そして研究支援という仕事を、業務を離れて観ること。
研究開発を支える仕事をして3年になります(就職を決めた時に考えたことの記録)。
仕事や組織の構造、研究開発業界の様子が掴めてきたと同時に、少し外から自分の所属する組織や科学技術というものを考えてみたいと思うようになりました。そして、研究者とは異なる視点と立場で、どう科学技術に携わっていけるかを、もう一度考えてみたいと思っていました(学生時代真剣に考えた研究者にならなかった理由の記録)。
いろいろな立場から、科学技術に携わる方が講師となるCoSTEPは、この2つの目的にちょうど合っていました。
- 講座を受ける中での喜びと苦しみ
学生時代以来久しぶりに、講義を受けたりして苦労したことや嬉しかったことを挙げてみます。
<苦労したこと>
・週1回、90分の講義を聴く事が大変
・自分自身がどう「実践」するかを求められる約月1回の課題が大変
・講義や、他の受講生の実践と、現実の仕事のギャップが大変
<嬉しかったこと>
・思考する機会、表現する機会が得られたこと
・新しい事を学ぶ喜びを思い出したこと
・近い志を持つ人とのつながりが得られたこと
受講し始めてまず一番に感じたのは、意外にも「講義を受けるってこんなに能動的なことだったんだ」ということでした。大学院時代には講義を聴くのは受動的でどちらかと言えば楽なことで、研究の計画を立てたり実験したり、資料を読んだりプレゼンを準備する方が能動的な作業で大変でした。一方で就職してからの毎日は、指示を受けて決められた事を早く円滑に処理することが求められる受動的な作業が殆どで、思考したり自分の意見を表明する余地がなかったんだということに気づきました。
授業を聴くということは、聞きながらどこまでを知っていて理解できているのかを考え、そこから考えられることを頭のなかで展開したり、わからないことを質問する。そういう能動的なことだったことに気づきました。その集中力を要する90分間を、週1回作り出すのが、大変でした。
また月1回程度、数百字の「モジュール課題」の提出が求められます。課題では常にどう「実践」するかを考えさせられるので、なかなか動けない現実を直視しなければなりませんでした。さらに、受講生がそれぞれ日々実践している「科学技術コミュニケーション」の情報が入ってくる中で、自分自身はどう動いて行くのかを考えさせられました。
集中演習で北海道大に行き、同じようにE-laerningで講座を受けている受講生と3日間を過ごしました。学生から社会人まで様々な立場の人が集まって、それぞれが書いてきた課題文を読みながら、考えて、理解して、意見を述べて、議論する。そういうごく当たり前だったことが、改めてとても新鮮で、こんなにも喜びだったのかと思いました。
講義は、毎回新しく知ることがあり、そこから自分で調べて考えたくなる刺激が多くありました。新しく学び理解することは喜びであることを思い出しました。
- 1年間の講座を修了して
選科Bライティング演習コースのテーマは「書くことは考えること、考えることは書くこと」でした。課題文等を書く中で、書くことが考えることだと実感しました。また、演習等を通して、書いて伝えることの技術も学びました。講義を通して、応募時の2つの課題も、答えはまだ出ていないものの、考えることができました。
新しい事を学び、考えて理解することは喜びであること。そして考えたことを表現し、他人と対話することで、さらなる学びにつながること。
この2つを改めて実感できたことが、CoSTEPを通して得られた成果だったのではないかと思います。講座を通して得られた、学ぶこと・考えることの喜びを、今度は科学技術という題材を通して得られるような場やコンテンツを作ってきたいなと思います。
(と書きながら、実際はなかなか何も動けていないのが苦しいところですが、、受講生の実践している様子を励みに細々進んで行ければと思います。)